FGO第二部 Lostbelt No.2 プレイ日記05 そこには炎が立っていた

第二章では、新所長が想像していたよりもずっと人間らしい人物だということが明らかになった。
あまり魔術師らしくはない、考えていたよりもお人好しな男だ。魔術の世界では生き辛そうにも見えるけれど、まぁ本人がわりとあんなノリなので、それなりに元気にやっていけるのだろう。
“ホムンクルス”への彼なりの思想みたいなものが、チラチラと見えるのもアポファンには興味深い。
関係ないけどなっ! みたいに言うのが全てツンデレ発言にしか見えない。


得た情報から至った、ダヴィンチちゃんの結論。
今までのゲルダの反応から、うっすらと感付いてはいたけれど、改めて言葉にすると重い。
文明も、魔術も科学もほとんど発達はしていない、完全に閉じられた北欧異聞帯における人類の環境。
家畜として飼われているかのようだ……というのは、神の意図が読めない以上は、まだ言い過ぎかもしれない。
だが印象的には、そんな感じだ。
多くを知らず、純粋無垢なままに“間引き”さえ前向きに受け止める人々は、純朴で優しくて綺麗に見えるけれど、汎人類史の視点から見ればやはり少し異常と言わざるを得ない。

苦しいのは、そんな北欧異聞帯のおそらく一般的な感覚を持つであろうゲルダが、主人公たちのような異分子にすらどこまでも好意的な点、だ。
何も知らない純粋無垢な彼女たちは、小さな喧嘩をすることはあっても、ひょっとしたら憎み合ったり敵意を向け合ったりすることさえ知らないのかもしれない。
それくらい無防備で、鈍感で、心優しい。素晴らしいことかもしれないけれど、そんなゲルダが真っ直ぐに好意を向けてくれることに、どうしても悲しさも感じてしまう。
そんな彼女に色々と質問をするのは、少し気まずくて辛い。
言い淀んでいるマシュや主人公を気にかけてか、言葉を続けてくれた新所長がちょっとオトナでちょっと格好良い。

しかし、汎人類史の話をゲルダにしてしまったのは、プレイヤー目線では少し早計ではなかったかなとも思える。
ゲルダが理解できないことをわかったうえで思わず、それこそゲルダのためではなく自分が納得できなくて、自分たちのために吐き出してしまったのだろうけれど、“正しく”はなかったかな、とも私は感じた。
第一章では後半になって、ようやくパツシィに真実を打ち明けた。そのうえで、最後には彼から、「他の世界を教えたお前たちを許さない」とまで、言われた。
あの言葉はパツシィなりの激励でもあったが、彼の辛い本音でもあったと思う。だからこそ、汎人類史の話を異聞帯の人々に語ることは、簡単にはしてはいけないのではないか……とプレイヤーの私自身は考えていたけれど、今回の主人公とマシュは、少し違った。
とはいえ主人公たちを責めることもできないだろう。
北欧異聞帯の状況は彼らの想定の範囲外で、更に明確に“人類が平然と間引きされる環境”を知らされて、どうしても疑問をぶつけずにはいられなかったのだろう。
彼らの弱さや若さの片鱗が零れ出てしまったようなシーンだった。
この後のワルキューレ戦についても、そんな感じかもしれない。

パツシィは、“自分には決して得られない幸せを教えられた”ことに憤ることができた。
ゲルダは、それすらもできない。それはパツシィもしくはゲルダのほうが強いとか弱いとか、個人に責任があるわけではなく、ほとんどは異聞帯の人類の在り方が決定付けていると言ってもいいだろう。
そういう意味では、パツシィとゲルダは全く違う人間で、全く違う異聞帯や人類の側面を主人公やプレイヤーに知らしめる、“見事なゲストキャラクター”という言い方もできるかもしれない。
ここで、最後にマシュはゲルダに謝罪した。
自分たちの事情を、自分たちの感情のままにゲルダにぶつけるような形になってしまったことを、マシュなりに悔いているのかもしれない。
ゲルダは知らない話をされても怒ったり嫌がったりするどころか、困ったうえで一生懸命考えて、笑顔で答えてくれようとする。
そんな姿が優しくて嬉しくてかわいくて、切ないぜ……。

翌朝、何かが始まるのか、騒いでいる集落の人々。
昨日は見掛けなかった若い大人の姿もあり、子供から花束を受け取っている。
ゲルダはこの日を“特別な日”と呼んでいた。
主人公やマシュは、その意味を今まで正確に理解できてはいない。
彼らを御使いだと思い込んでいるゲルダは、今まで何も教えてはくれていなかった。
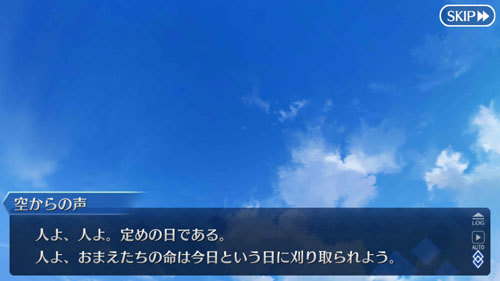
定めの日、定められた人間がヴァルハラへ行く日。
大人や子供の呼び声に応えて、上空から謎の声が降ってくる。
それにマシュは、強力な魔力反応を感知した。

始まろうとする儀式を、主人公たちは思わず止めてしまった。
下総国やロシア異聞帯では我慢できていたのを、今回できなかったのは、やはり昨晩のやりとりを引きずっていたからかな。
マシュが戦えるようになったこと、そして異聞帯切除の負担が重すぎて悩み過ぎて、やや前のめりに気負ってしまった部分もあるだろう。

御使いの行為を止めることが、将来的にプラスになるのかマイナスになるのかは、現時点の主人公たちにはわからない。
確かに我慢ならない場面ではあったけれど、飛び出してしまったのはやや短慮だったと言わざるを得ないかもしれない。
“大人になるまで生きられない”北欧異聞帯の人々に、マシュはかつての自分を重ねてしまったりもしたのかもな。
後になれば、冷静になれば落ち着いて判断することも振り返ることもできるけれど、この瞬間の彼女たちは、飛び出してしまった。

次々に現れる御使いに対して、戦力は心許ない。
このままでは倒れるかもしれないと、マシュも気付いている。
そしてゲルダは、こんな場面であっても「御使い同士で喧嘩をしないで」と、選ぶ言葉が拙く幼くて優しい。
ちょっとだけ怖いけどいいの、という彼女の言葉に対して、主人公は非常に強い口調で反論をした。
ここまで感情的、かつ視野が狭まっている主人公の姿はわりと珍しい。
それが良い悪いではなく、この場面での主人公は心の底から熱くなっていて、冷静な思考ができない状態に近かった。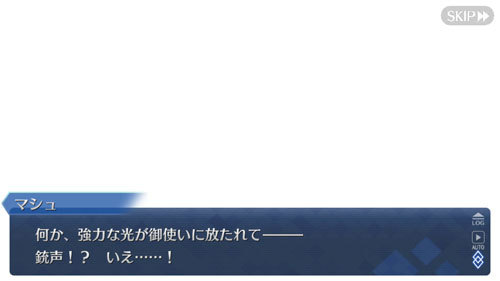

主人公と共に、戦闘の続行を決断するマシュ。
我武者羅に、拙いくらいに後のことなど考えず、ぶつかっていこうとする彼女たちの前に、それが現れた。
「彼」が来てくれたのは、物語の都合といえばそれまでだが、主人公やマシュが抗ったからこそだとも思う。
マシュが時間を稼ぎ、粘り、戦略などないままにギリギリまで戦ったからこそ、彼が間に合ったのだろう。
そして、そんな主人公たちだからこそ、彼は手を貸してくれたようにも思う。

重く停滞していた北欧異聞帯の空気を、スカッと明るく照らしてくれる男ッ!!
ナポレオン、現るッッ!!
……いやー、熱い。嬉しい。楽しくなってきた!
北欧異聞帯の序盤は重たい真実がどんどん明らかになっていく一方で、どうしても気持ちが沈みがちだった。
そういった暗くてジメジメしたものを、吹っ飛ばしてくれたナポレオン。まさに快男児。

ナポレオンの名乗りが、また熱くて格好良くて名文なのだが、スクショを並べるには長すぎるので中略。
初対面なのに「わかった! アンタについていくッッ!!」と言いたくなるような、ともかく超カッケー男だ。
細かいことはよくわからないけれど、たぶんナポレオンは超良い奴なんだろうなとこのシーンだけで判断してしまう私だった。我ながらチョロいぜ。
裏切る可能性なんて欠片も想像していなかった。ちょっと嘘。